村が壊れた後に――NHKドキュメンタリー『巨大開発』(1973) 視聴の記録
1 前提
2000年、ミレニアムの年に最初の『NHKアーカイヴス』の放送があって、6月ごろから年度末まで私は毎回それらの番組を録画しては見ていた。それまでドキュメンタリーというものを意識してまとめて見たことはなかったのだが、映像なるものについて何がしかのことをぎりぎり考えなくてはならない局面がそのころ個人的に発生したので、ひとまず見られるものを何であれ数多く見ようとしていたのである。その年に私が見たものは多くが1960~70年代のもので、時に50年代のものもあり、60年代生まれの私にとって古いものはそれなりに珍しかった一方、70年代以降のものはリアルタイムでむかし目にしたドキュメンタリーの懐かしいトーンを湛えても見えた。時折「ドラマ」と称するものがあった。ドラマといっても多くの取材資料に基づいた、ドラマ仕立てのドキュメンタリーなのかドキュメンタリー仕立てのドラマなのかよくわからないあたりの、例えば多くの若者に取材して得たのであろうものごとを、ひとりの青年の身に起こったさまざまなできごとと内心の葛藤、青春の遍歴の筋に仕立てて、当時の世相とその中で揺れる青春の物語として描きあらわそうとしたものであるとか、そのようなものにも、70年代においてはまだ「これはイメージです」とか「再現映像」とかの妙に言い訳じみた(しかも語義的に厳密に考えれば全く意味不明な)字幕が入ってはいなかったので、「ドラマ」を見終えた後に続くスタジオ解説を注意深く聞かなければ、それが「ドキュメンタリー」でなく「ドラマ」であったということはほぼ全くわからないであろうと思われた。ドキュメンタリーとフィクションの間に(少なくとも映像論的には)線など引けないという確信はそういうものを多く見る中で自然に深まった。ドキュメンタリーと銘打たれた作品にせよニュース映像にせよ、全て、「ドラマかもしれない」とあらかじめ疑って見るようになったのである。そしてそれは――ドキュメンタリーかフィクションかというのは――本質的にたいして違わない、最終的には全くどうでもいいことなのであった。ドキュメンタリーであろうとドラマであろうと、それらは個々の作られ方において、作られた時代の世相を色濃く反映する。

例えば1973年12月に放映された『巨大開発』というドキュメンタリーは青森県六ケ所村が「舞台」となっていて、きつい青森訛りの村人たちが大勢「登場」するが、標準語字幕など一切ついていないので、まことに聞き取りにくい。インタビューに答えているところはまだしも、村人どうしが何事か相談したり論争したりしている場面では、何を相談しているのか場面まるごと全く聞き取れない箇所すらある。1973年放映当時、各地の方言は今よりもはるかに強く広範に残っていて、地方へ行けば人々は固有の方言で喋っているというのはかなり当然の事実であったし、目の前にいる人のきつい方言を聞き取らねばならないような局面も、今思うほど珍しいことではなかっただろう。2000年に初めて見て以来、大学の若い学生たちにこの『巨大開発』をしばしば見せて、どのように見えるのか尋ねた。方言が聞き取りにくくて大変だという感想は当初から当然あったが、近年では、「こんなにきつい方言なのに、なぜ標準語字幕がついていないのか」「字幕がついているべきだ」という意見を聞くようになった。確かに、2021年の現在この番組を全く同様に制作するならおそらく標準語字幕がつくのだろうが、聞き取りにくいとはいっても、枢要な場面々々においては、耳を澄まして聞きさえすれば、語法の細部までは聞き取れなくても大体どんなことを言っているのかはわかるし、「真実は声の響きにある」などというソクーロフばりのことを考えて作られた作品なのかどうかは不明だけれども何より声のトーンから、そのつどどういう方向性のことが言われようとしているのかは相当明瞭にわかる。それで充分だと判断されたからこそ73年のこの番組には字幕がついていないのだろうし、村人が語るひとつひとつの語句まで視聴者に正確に理解してもらうことは、別にこの番組の目指すところではなかったのだろう。映像作品における方言の扱いというのはかなりセンシティヴな問題であり、「なぜ字幕がついていないのか」と問うよりもむしろ、「現代ではなぜ字幕がつくのか」と問うべき問題であるように思う。「こういう方言が語られるときには字幕があって当然」という認識が2021年現在相当に行き渡っているとおぼしいが、それはそれで言語ナショナリズムの新たな現代的様相のひとつである可能性はある。この問題に踏み込むことは今の私にはできないし、方言に字幕をつけることの是非をここで論じるつもりもないが、ほとんど聞き取れないほどに訛りの強い方言を喋る農村の人々と、比較的訛りの弱い喋り方をする「社長」「県庁職員」などの人々、そして標準語のナレーション、それらの間のいわば方言的階層性のようなものは明瞭に感じられ、それは実は意図的な編集によって浮き彫りにされたものものでありうるとは、大いに考えられるところだ。
上で触れた青春グラフィティ・ドラマのように、実はこの『巨大開発』も「ドラマ」であったとしてもおそらく別におかしくはないだろう。「このドラマはフィクションです、実在の土地や人々とは何ら関係ありません」などと冒頭に記されていたならば、70年代の「とある村」で起こったできごとを、種々の取材に基づいて迫真的に描いたドキュメンタリー・タッチのドラマだと思って誰もが見るかもしれない。短いイントロの後、激しく揺れる菜の花にかぶせて題字が出ると同時に差し込んでくる不穏で劇的な音楽の、その差し込まれかたにせよ、ラスト近くの「クライマックス」へ向かう盛り上がりの作り込みかたにせよ、それはそれは「ドラマチック」である、ともいえる。ひとつひとつのシーン、ひとつひとつのショットに、ドラマ的な演出が施されているように見える。例えば学生たちが必ず指摘するのは、冒頭から5分経ったあたりで六ケ所村開発推進派の実業家がインタビューを受けるシーン、開発受け入れの利点を語るその顔を映していたカメラがふと頭上の豪華なシャンデリアにティルトアップするところで、それは言ってみればちょうど、何かの刑事ドラマで容疑者の金満家の事情聴取の最中に、主だって質問をしている刑事について歩いている新人で庶民派の若手刑事が、余裕綽々と近況を語る金満家の顔からふと苦々しく目をそらして天井のシャンデリアを見上げるシーン、のようなシーンであり、敏感な学生たちはそこに一種の明瞭な「あざとさ」、開発推進派の実業家というものと「利得」を結びつけながら「金持ちがいい気なことを喋っている」という印象をあからさまに形成しようとしているという恣意的な映像編集戦略を読みとる。冒頭からここまでの5分間、ナレーションに導かれて視聴してきた視聴者において、ここではすでにナレーション目線で画面を見る体勢が確立しているから、あたかも刑事ではなくナレーター(によって代表される視線主体)が、実業家からふと目をそらしてシャンデリアを見上げたかのようで、「金持ちがいい気なことを言いやがって」的な「目線」へと自然に、ないしは強引に誘導されようとするのである。しかしこの種の組み合わせ、すなわち、ある種のお偉いさんと頭上のシャンデリアという組み合わせは、現代ではすでに食傷されつくした周知の定型をなしているから、ここでそのように誘導されようとしているということに比較的誰でも気づきやすい。私もむろん初見のときにはこの「あざとい」誘導に目を引かれたが、それと同時に、このようなシャンデリアを頭上に戴き皮ソファにどっかりと腰を下ろしてこのような喋り方をするお偉方というものが実際にいたのだということにひどく驚いたものであった。「工業開発によってだヨ、ワレワレも所得が増えるような開発が来ることはネ、これァ、(人差し指を振る)アーナタだッテ! 賛成するだろうと思うんです(大きくうなずいて微笑む)。そういう開発に反対するということはネ、私には考えられんです。いや、私はネ……」あるいはまたもっと後のシーンで別の開発側の「社長」が、やはりソファに腰を落ち着けて悠揚迫らぬ口調で「それから一番大切なことはネ、これは私いつも言うんですけどもネ、このー、土地を買わしていただくなんてことはネ、りんごを買うのとは違うんだと。こういう、地方の農民の方々の土地というものは、生活それ自身ですから。(……)生活を買わしていただくんだと。それだけに、ヒジョーゥに意味が大きいんですネェ」などと、やや顎を上げぎみの微笑を湛えつつ語るとき、私はつい手塚治虫のマンガなどにしばしば登場する利己的な成金社長や悪徳議員の姿を連想し、貧困にあえぐ人々を目の前にしてひとり高価な葉巻をふかしつつ「人生はネ、きみィ、努力だよ努力、わかっとるかね、ええ?」などとほざいて回った挙句ラストで天罰を受けるたぐいのキャラクターをここに重ねて見てしまいそうになるのであった。そして上のように、せりふを引用するさいにところどころ「ネ」とか「アンタ」とか「ヒジョーゥに」などとカタカナ書きしてみると、いよいよその種の類型にあからさまに近づくことに驚くのだ。しかしそれはそれで、これら「実業家」や「社長」に対して不当な見かたであって、「実業家」がインタビューを受けているときにソファにどっかりと腰を下ろしていてその頭上に豪華なシャンデリアが輝いていたのは事実であるとしても、そこはひょっとしたら自宅ではなく商工会議所の応接室か何かで、「今は開発に便乗した形でやっているが……あくまでも地域の住民を支柱(?)にしてやっていきたい、これは私の夢だ」と語る彼自身が、「地域みんなで豊かになっていこうじゃないか」ということを訴え、人々をその方向へ引っ張っていこうと真摯に考えて資金を出して内装に手を入れ、あえて豪華なシャンデリアを設けたとか、そういう場所であるのかもしれない、それを、そのように語る彼の顔から不意にティルトアップしてシャンデリアを大写しにするのは撮影者であり、このままでは生活が成り立たないと深刻な顔で縷々と訴える「地域の農民の方々」との対比において見せようとするのは編集の手際である。つまり私が驚いたのは、「住民のみなさんを大切に」等といかに志深く語ろうとも、金満家の世間観は庶民のそれと懸け離れて結局はみずからの利得へ行きつくのみだというお偉方像、マンガチックにシンプルでわかりやすい類型化は、マンガ家固有のものでは別になかった、ということに対してなのだった。こうした「おえら方」類型においてマンガが先か実写が先かなどというのはそうそうわかることでもない。それはもっと古くまで遡って観察しなければわからないことではあるけれども、高度成長期からオイルショックを経た70年代半ばにかけて定着していったのではなかろうか。経済成長によって巨利を得た人々と得なかった人々の明暗の差を、社会問題としていやましにくっきりと映し出すための斬新な手法として、この種の「見せ方」が流通したということなのかもしれない。なにしろこの類型は強烈なものとして広く流布した。それから40年以上を経た現代の私たちはこうした「見せ方」を「あざとい」時代遅れの偏向報道と感じる。多くの学生たちは、このあたりでさっそくイヤになって、視聴するのをやめてしまう。
NHKアーカイヴスで見られる、6~70年代の番組の多くはどちらかといえば「左寄り」であって、権力側とそれに抑圧される人々という対比図式が成立する場合には必ず後者の側に立ったスタンスで製作されている。『巨大開発』などは比較的公平な、というか、なるべく公平な視点で番組を作ろうという意図が感じられる類であると私などは思うが、それでも上記のシャンデリアのシーンに見られるような強力な誘導性がそこここに埋伏されてはいる。もっと冒頭のほうで、「正式な計画が発表される前に、県外の不動産業者が村に乗り込んだ」というナレーションとともに、スーツやラフなジャケット姿である種特有の闊歩のしかたをするガタイのいい「不動産業者」たちと、彼らが運転するらしい自動車の群れが、未舗装の村道の幅いっぱいに「乗り込んで」くる様子が映される。「開発区域が明示される前に、およそ1700ヘクタールが彼らの手に渡ったという」。その直前に「農業に熱心な一家」の田植えの様子が映し出された後でこのナレーションを聞き自動車が連なる画面を見て、これら「不動産業者」なる人々をある種の、現代言うところの反社会的なそれと思わない者が果たしてあるかどうか。のちに同様の風体をした「県外の家畜商」が、補償金を受け取って酪農をやめ市内での貸家業へ転向しようとする主婦から十数頭の酪牛を買いたたき、やはりガタイがよく一種特有の風体をした「市内の不動産業者」が米軍向けの貸家を斡旋しようとするときに、世慣れぬ「おばさん」が口八丁手八丁の彼らに今にも丸めこまれ騙されようとしているのではと思ってハラハラしない者がいるだろうか。実際は、むろんどうだったかわからない。さんざん値切られたあげくに牛の代金として札束を手渡され、その場でもう一度指をなめながら札を数える「おばさん」の表情は、辛く寂しげであると同時に実に卑しげにも見えるし、「業者」たちの顔のアップがほとんどなくその表情がはっきりと映ることがないのも、後ろめたいことがあるから当人たちが顔を映して欲しくなかった等の可能性も大きいけれども、実はそうでもなくて、いかにも善意と思いやりに満ちた表情がそこに映し出されてしまうことが周到に避けられた結果だったという可能性だってないわけではない。開発派の実業家からシャンデリアへのティルトアップと同等の誘導性は、開発反対同盟のリーダーだという盲目とおぼしい黒眼鏡の男性から、卒中の後遺症なのか激しく震える彼の右手へのティルトダウンにも遺憾なく見てとれる。全編のクライマックスを構成する村議会での大混乱の場においてその震える右手は、開発受け入れを暴力的に決議断行した(と反対派は言う)賛成派への、反対派の憤り、文字通り身も震えるような怒りをダイレクトに表象するが、そこに感知される編集の「あざとさ」はシャンデリアの「あざとさ」とほぼ同質であるだろう。シャンデリアを戴く「実業家」の姿に下卑た俗物性を感じ取って反発を覚える視聴者がいるとしたら、その視聴者はおそらく、顎をしゃくりながら上から目線で開発反対論をぶつ野党議員のアオリで撮られた表情にも同じ反発を覚えるに違いない。どちらかといえばかなり明瞭に反対派寄りに構成されていても、番組全体として見れば、開発賛成派の映り方にも反対派のそれにもほぼ「対等」と言ってもいいような「あざとさ」が仕込まれ、賛成理由を語るお偉方の独善性にスポットが当たるのと同様に、新設された銀行の誘いにやすやすと乗って早々と融資を受けてしまいのっぴきならない羽目に立たされた(とナレーションは言う)人々が銀行主催のパーティでごちそうをむさぼり食う愚かしい表情にもやはりスポットは当たるし、反対派賛成派を問わず地位ある人々はそれぞれに俗物的な醜さを付与されながら、その一方、実業家だって何も太平楽を吹いているわけではなく彼らなりに真剣にやっているのだということがそのまなざしの光からわかりもする。
それらの様子が、1972年当時の六ケ所村の実態を「ありのままに」反映しているなどと考えることはむろんできない。NHKアーカイヴスのHPによればこの番組制作にあたり取材陣は「開発前夜の六ケ所村を1年にわたり長期取材」したとあり、その結果をたった45分の番組にまとめる時点で、どういう素材をどのように組み合わせてその45分を構成するか、取捨選択の過程で、いかなるものであれ偏りが生じないわけはないのであり、どんなに公平な視線の持ち主が制作にあたろうとも、完全に客観的で公平なスタンスの番組など、作ろうと思えば作れるだろうと考えるとしたらそれは大いに甘いのである。そもそも切り貼り編集でできている映像作品なるものにおいて何らかの「真実」が映し出されているとすれば、それはその映像においてのみある「真実」であって、現実世界、すなわちこの場合は1972年の青森県六ケ所村が事実どのようであったかという意味での「真実」とは基本的に何のかかわりもない。この番組を見る限りでは、「村はまっぷたつに」賛成派と反対派に割れたかのようだけれども、実際には、賛成派でも反対派でも別段ないままにただ生活に押し流される形で土地を手放し、あるいは手放さなかった人たちが人口の多くを占めただろうし、金満家ではない賛成派の人も、富裕な反対派の人もいただろう。番組が単発の45分ではなく1時間の6回シリーズか何かであればそういう人たちも定めし登場しただろうが、実際には、何人かの実業家や議員、村長、「県外の業者」たちの他には「新納屋地区」と「上弥栄地区」のふたつの地区のそれぞれの「一家」とその隣近所の人たちしか(少なくとも名前が出る形では)登場しない。新納屋地区の「佐藤さん一家」は、開発を不安に思いながら伝統を守って淡々と稲作を続け、上弥栄地区の「戸田さん」は酪農をやめて土地を手放し、市街地へ移住しようとする。他の地区の人々、他の立場の人々がどのようであったかについては、この番組の外に出て、他の資料を当たるなり別途取材しない限り知りようがないけれども、それをことさら知りたいというのでもなかった。私がそれを知りたくなったとすれば、画面に吸着されつつ番組を見るところからふと我に返って、続くスタジオ解説を聞くなどして改めてこの作品の背景にある歴史に興味を持つ局面においてであって、とにもかくにもこの『巨大開発』を現に視聴しているときには、私の眼の前の「六ケ所村」と呼ばれる村では、来るべき工業開発を前にしていくつかの立場の人たちが、それぞれ異なる思いを抱えて暮らしている、そしてその立場の違いがやがて先鋭的な対立と諍いへと進展してゆくということがまざまざと起こっていたのであり、それが目の前で起こっているという局面において、その「六ケ所村」と呼ばれる村が、実在の同名の村と同じであるかどうかはあくまでも二の次であるのだった。六ケ所村といえば今でこそ原発廃棄物処理の大規模施設のある場所として有名だけれども、そのことを知らなければ、ことさらに青森県六ケ所村でなくとも長野県八ヶ岳村であっても、初見時の見え方に変わりはなかったであろう。だから、ここまで長々と書いてはきたが、私が20年以上のこの『巨大開発』を頭の片隅に納めて忘れず、機会あるごとに何とか取り組んでみたいと思いつづけてきたのは、上記のような類型の用い方や誘導的なカメラワーク・画面編集のせいなどでは全くなかった。それらはむしろ枝葉末節にすぎなかった。
2 震撼
初見時に私の耳目をひどく惹いたもののひとつが、三カ所に挿入される無音のショットであった。一度目は、新納屋地区のお盆祭りの時期に若者たちが都会から里返りしてくるシーンの途中、久々に再会した同級生どうしなのか路上で笑いさざめき踊る若者たちの屈託ない様子に、ラジカセから流れるポップミュージックがかぶる、その音楽がふと途切れ、画面が切り替わり、一瞬、ユリの花が映る。ものの1秒かそこらで画面はまた若者たちに切り替わるが、ややあって再度音楽が途絶え、画面は今度は草原に静かに立つ一頭の馬を映し出す。10秒足らずの間、無音で、馬だけが穏やかにたたずむ、と思うと再びラジカセの音楽と若者たちなのであった。


三度目は、番組後半、村議会の混乱のシーンの直後、川面にたゆたう白鳥の姿がやはり無音で映し出されるが、直前の場面が騒乱の極みであったゆえにこの無音はたいそう印象的である。十数秒続く無音の白鳥のあと、場面は新年の準備をする新納屋地区の人たちの穏やかな餅つきの光景に移る。「政争のざわめきもここには届かない」と言うナレーションから察するに、無音の白鳥や馬は、世知辛い喧騒に満ちた人間の生活と、政争などどこ吹く風と悠久の中に変わらず存続する「自然」の営みとの対比のために挿入されているのだろうなどと、穿ったような解釈を施し、そこにある種の「あざとい」演出を見てとったりすることはむろんできる。しかしそれなら、何も無音でなくとも、馬や白鳥に添えて草原の風や川面の水音などの自然環境音が入っていても同じことだろうに、この三つのショットが環境音さえ排除された完全に無音のショットであることが、私をひどく落ち着かなくさせた。そこではナレーターは沈黙しているのではなく、存在を休止していた。それまで何となくナレーター目線にのっかって視聴していたのが、ふいに足場をはずされる感覚、残留視線の不安が回帰してくる強い感覚にみまわれるのである。この馬は、白鳥は、いったい誰が見ているのか。私はなぜそれを見ているのか。私はいま実在の六ケ所村のできごとを見ているのではなく「映像」を見ているのだ、という局面に、意識が引き戻される。

同様の「引き戻し」は、上弥栄地区の「戸田さん」が「県外の業者」から金を受け取った直後のシーンでも強く感じられる。こうして牛を売って牧場を手放してしまえば後は所詮居食いするしかなく、都市に移住すれば日々の入費も地代もばかにならないから補償金などいくらもらったところであっという間になくなってしまう、牧場も一昨年あたりからやっと軌道に乗ったところなのに、本当に悔しいというようなことを、妙に滑らかに淀みない方言で語るらしい「おばさん」の顔から、ふと画面が切り替わると、戸田家の牧場を囲むとおぼしい丈高い芦原の向こうから夕陽の色が差して、湾か湖か川か、その黄金色の水面の照り返しが草の間からまぶしく透けて見える景色が、ちょうど車ですみやかに通り過ぎるがごとき速度で右から左へずっと流れていく。あたかもその景色が窓の向こうに見える車に乗って「戸田さん」が移動しながら語っているかのようだけれども、「戸田さん」はそのショットをはさむ前後のショットでは同じ牛舎にいながら語っているのだからそんなはずはなく、ではいったいこの美しい黄金色の景色が流れゆくのをこうして眺めているのは誰なのか。あるいは、そこでまことに聞き取りにくい言葉で、しかし滑りゆく風景に合わせて滑るように淀みなく語っている声は本当に「戸田さん」の声なのか。

「戸田さん一家」――といっても母ひとり子ひとりで、父親は出稼ぎ先の埼玉で事故にあい入院中とのことだが――のみならず上弥栄地区の酪農家はみな揃って補償金を受け取り酪農をやめる決断をしたとのことだが、その合意、あるいは個々の酪農家がそうした決意に至った経緯は詳しくは語られない。悔しいと言いながら戸田家が反対派に回らず酪農を離れる決断をした事情もよくはわからない。「戸田さん」が登場するときにはほぼ常に息子の光志(みつし)さんが影のように付き添って登場するが、彼は番組を通じて一言も口をきかない。ひょろりと痩せて、およそ牧場の激しい肉体労働には向いていなさそうなこの19歳の青年が一連のできごとをどのように受け止めているか、自分と家族の将来について何を考えているか、全く何ひとつ明かされることがない。画面に登場している時間の長さでいえばおそらく彼が最も長いのだが、にもかかわらず一度も声を発することがないのである。それを言うなら、新納屋地区の農耕家族を代表する「佐藤さん一家」の「佐藤さん」も実は一言も口をきいてはいないのだが、彼の登場は少なく、また彼や彼の父親とおぼしい老人が「開発」をどう考えているかについては、ナレーターが「やりかたが一方的なので、土地を離れる気はない、と佐藤さんは語った」などと、間接話法の「引用」としてその「内心」をも代弁してくれるので、そのナレーションと同時に画面に映る佐藤さんが口をきいていなくとも、単に「寡黙な人」という印象を与えられるのみである(その印象が実在の佐藤さんに適合するものだったかどうかは、言うまでもなく全くの別問題であるが)。その一方で「戸田光志さん」についてはそのような「内心の代弁」的な引用が行われることが一度もなく、単に無口な若者といってはすまない、何か頑なな沈黙、恣意的な無言を付与されてそこに呈示されているように見える。
彼はまた45分の番組の中で唯一、カメラによって回り込まれる人物でもある。ほとんどの場面において画面は、取材班のカメラが目の前のものを撮りましたという態の構図になっているのだが、売った牛たちがいよいよ車に積まれて運ばれていくのを「光志さん」がひとり見送るそのシーンだけ、カメラは彼をめぐってドラマチックと言ってよい回り込みを見せる。そして回り込まれてもなお彼は無言で、牛が売られていくのを見送りながら何を考えているのか、その無表情からは何ひとつ読み取ることができない。このときはナレーションによる「代弁」が入るが、そこで「…と光志さんは語った」として語られることは、牛が売られていくのを見るのが辛いからといって母親は出かけてしまったということ、そして、その「母親の願いなので、牛の写真を一枚でいいから後で送ってくださいと我々に頼んだ」ということのみであり、当の「光志さん」自身がそうしたことをどう思っているかについてはやはり一言も語られないまま、「光志さん」の後ろ姿にかぶせてさらに「上弥栄開拓地、満蒙からの引揚者によって開拓されて25年、その歴史はこうして終わろうとしている」とナレーションが語る間にカメラは「光志さん」の正面に回り、やや引いて、畜舎の前に腕組みをして無表情でたたずむ青年の姿を捉える――そしてしばし、そのまま無音のショットとなる。単にトラックが去り「光志さん」が喋らないがゆえに静寂が落ちるのではなく、馬や白鳥のシーンと同じく無音になっているようであり、そのことがまことに不穏な感触を私に与える。馬や白鳥と同様に「光志さん」もまた、人間社会の喧騒から一線を画したところに営まれながら人間社会と共に破壊されてゆく運命にあるものとして表象されているのか? あたかも「声なき自然」の一環ででもあるかのように? 反対派にも賛成派にも組することなく、ひとりユリや馬や白鳥の側に立つ者であるかのように? そういう考えは――とても私の気に入らなかった。声にならないさまざまな思い、安易な表象化を拒む錯綜した一連のものごとを一身の沈黙の中に引き受けながら、「戸田光志」という名を仮初に与えられたあの人物が、他ならぬ表象不可能性のアイコンとしてそこにひそやかに据え置かれているのだというような考えは。しかしそれでも、あらゆる登場人物が何事か語りながら/語らされながら何かの文脈の中にすっぽりとおさまって見えるよりは、まだしもましなのだろうか?


原爆映画をその専門とする映画学者の片岡佑介氏はしばしばその映画論の中でミシェル・シオンの『映画における声 La voix au cinéma』を参照し、最新の講義(一橋大学2021年度共通教育リレー講義「人文学入門(総合)」)でも、「トーキー映画において、まだ一度も音源となる姿を見せていない声」としての「アクスメートル acousmêtre」と、「トーキー映画において、まだ一度も声を発していない人物」としての「ミュエ muet」とを対のものとして紹介してくれている。シオンによればこの二種のものはそれぞれ映像において特異な力能を発揮するものであるそうだが、片岡氏のまとめによれば「アクスメートル」すなわち「身体なき声」とは「発声者の身体が未だ見えず、影等を通じてしか現れない有力な存在の声」であり、「画面の身体に繫留されないことで「同時に内部でも外部でもある〔画面の〕表面を漂い」、そのため「偏在性」と「すべてを見通す」力を備え、「掟であるかのように現れる」」。他方、これの「片割れ」である「ミュエ」はすなわち「声なき身体」もしくは「沈黙の人物」であって、この「声を発しない無言の人物は、物語の「探求の鍵となる究極の一声を匿っているように推定され」るばかりか、「声に縛り付けられない」が故に「空間における境界の不明瞭な位置を占め、いつでも画面外から出現するように見える」ものである。そして「両者は映画を構成する聴覚的/視覚的表象のいずれかを互いに欠いているため、音と映像が想像的に結合されることで構築される物語空間に明確な位置を持たず、それが両者を特別な存在たらしめている。その意味で両者は相補的といえる」と(以上、片岡佑介「黒澤明『生きものの記録』における〈核〉への恐怖を蔽うものについて」『言語社会』第7号、一橋大学言語社会研究科紀要、2013)。このことを2013年前後に片岡氏から初めて教示されたときに私が「ミュエ」としてまず思い浮かべたのは、他ならぬこの「戸田光志さん」であった。その氏名を記した字幕とナレーションを伴う彼はさすがに「画面外から出現」するようには見えないものの、上述のように馬や白鳥と同程度には、開発をめぐるコンテクストの外に置かれているように見えなくもないのであった。上記の最新講義によればまた、ミュエは声を発しないがゆえに観客は「映像を目の当たりにするしかな」く、その「内心を読み取る」ことができない――言い換えるならば、内心なるものを正しく読み取ったと信ずべき確証をもたらす言語的文脈を与えられない――ので、「映像」が「本来もつ不穏さ、衝迫力」がそこには凝縮してあらわれるのだといい、またさらに興味深いことには、自らが言語を発しないがゆえに、外部から容易に文脈化されうる「従属性、受動性ももつ」ところが、「映像」というものそれ自体の本質に直結しているのではないかという。多くのナレーションによって「代弁」されている「佐藤さん」は「戸田光志さん」よりもはるかに「文脈化」されているといえるだろうし、ナレーションのつきかた次第では、また視聴者個々の見かた次第では、「光志さん」といえども「佐藤さん」同様にたちまち「容易に文脈化」される可能性がいくらでもあったに違いない、それが実際には、意図してかせずにか、「光志さん」がどういう人であるのかを示唆するような言葉、例えば「親孝行な」とか「働き者」とか「物静かな青年」といったような、およそ属性に触れるような形容は何ひとつ付与されておらず、あたかもその種の属性化の一切が周到に回避されたかのようであり、盆休みに帰省してきた若者たちと彼がどういう関係性にあるのかも全くわからず、彼自身に関するほぼ全てのことは、その像において秘匿されている。――もっとも盆休みの若者たちも実はセリフらしいセリフは一言も発せず、互いに笑いさざめいているだけなので、音楽を伴うからにぎやかに音声を発していると見えながらその実、若い世代全体が、馬や白鳥と同様の外部的位相にあるものとして、いわば沈黙の影のようにそこに揺曳するものとして映し出されているにすぎないのかもしれないのだが。開発が来ようと来まいと多かれ少なかれ都会へ流出していくであろう若い世代は、開発をめぐる村の動揺という文脈から、すでにあらかじめ外れていて、盆の時期にたまさかバイクに乗って帰ってくる彼らは、つかの間あの世から立ち戻ってくる精霊同様のspookyな現象にすぎないのかもしれなかった。だとすれば同世代の「光志さん」もまた、なぜかいまだこの世にとどまっているにせよ、本質的には彼ら同様、「外部から出現する」性質の存在であるのかもしれない。そして、にもかかわらずなぜいまだにこちら側にとどまっているのか、それもやはり彼の沈黙において秘匿されていることのひとつなのであろう――
しかし、そのようなことを私にとつおいつ考えさせるものとして「光志さん」のミュエ的なありかたが浮上してきたのは、実は初見時からすでにかなり経った後のことであった。馬や白鳥の無音の場面や、黄金色の芦原が流れる場面の不穏さもさることながら、初見時に何よりも私をして震撼せしめた場面は、村議会騒乱から新納屋地区の餅つきの場面、賛成・反対両派の「リコール合戦」の様子を経た直後に訪れた。旗色の悪い反対派のリーダーである村長がひとり書類を整理する背に、「任期満了を目前にして、身辺は騒がしい」というナレーションが入った後、場面は切り替わって、北の海辺に打ち寄せる荒れた波濤が大写しになる。無音ではなく、暗く曇った空を舞いつつカモメが鳴き、人の背ほどはあるように見える怒涛が画面手前へまっすぐ押し寄せては砕けるその音が轟く中、ナレーションが淡々と言う。
村のある人が、われわれに語った。開発といっても、実際に工場が来るのはまだまだ先のことでしょう。公害防止の技術も進んでいくはずです。しかし、工場や公害が来なくとも、もう、村は壊れました。
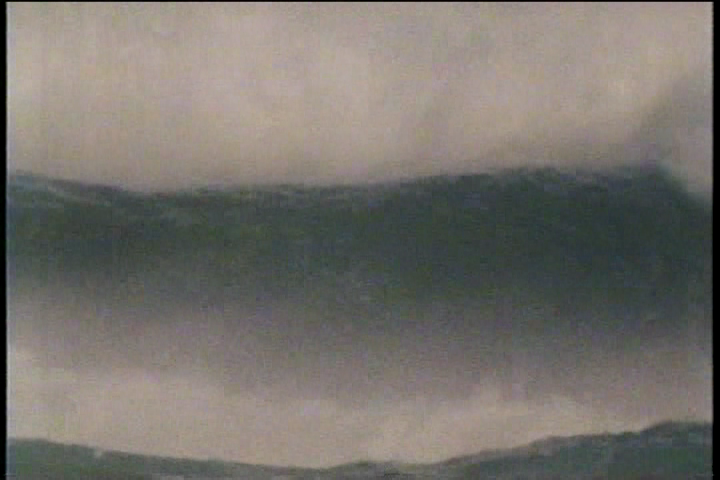
それからすぐに「光志さん」が牛を見送るシーンになるのだが、初見のとき私はおそらく、その牛のシーンを、あるいは無言の「光志さん」をめぐるカメラの回り込みなどを心にとどめる余裕などほぼ全くなかったであろう。その直前、「もう、村は壊れました」という声が、荒れる海の波濤そのものであるかのごとくに轟き渡るのを聞いたように思い、私の耳目は半ば麻痺していた。そのとき私が被った麻痺的な震撼は、しかしながら、「村が壊れてしまった」という意味内容によるものではなかったのである。ひとつの村が壊れていくありさま、「まっぷたつに割れ」た村で、議会をも商工会をも農村共同体をも分断と軋轢が侵蝕していくありさまはそれまでの30数分で遺憾なく見せられ聞かされてきたのだし、その種のストーリーそのものは、何も初めて聞くような話ではなかった。ナレーションが語る声を聴きながら、「工場や公害が来なくとも、もう、村は」と言われた時点で直後に来るのはおそらく「壊れた」というような単語であろうと瞬時に予測さえしていたのであって、次の瞬間、予測通りに「壊れました」と言われたからといって、意味内容の上でそこで震撼させられる理由など何ひとつなかったはずなのである。にもかかわらずなぜ震撼させられねばならなかったのか、それを、いつか解くべき謎として、2000年以来だいたい1年に1度くらいずつこの番組を見直し続けてきたのだったが。アクスメートルやミュエのことを勉強させてもらったりしながら20年経った今でも、初見時からすでに漠然と感知されていた以上のことが何か明瞭になったわけでは残念ながらない、と言わざるをえないが、それでも、これらの映画用語が謎解きのための貴重な手がかりをおそらく私に与えてくれる。
3 判決
アクスメートル、すなわち「一度も音源としての姿を見せない」まま発せられる声、と呼びうるものはこの作品においてはナレーションのみであるが、ふたたび片岡氏の最新講義によればアクスメートルは「観客による映像の理解を規定する(=文脈化する)」強い力能をもつということであるから、発語者の姿が映らないナレーションというものは一般にある種のアクスメートルであると言ってよいように思われる。しかしこの『巨大開発』においては冒頭からほぼずっと一貫してナレーションが観客を導き続けてきたのであって、その点、この海のシーンのみ特異であるわけではない。いかにもNHKらしく淡々と棒読みに近い語りであり、感情を極力排したとおぼしい、しかしながら非常に繊細な棒読み――イントネーションおよび、語と語の間のマというか呼吸がたいへんプロフェショナルに緻密に計算された棒読みで、ベタにドラマチックな演劇的な読みかたになるぎりぎり手前にふみとどまっている棒読みである。それゆえにこそ漏れ出る抑えた情感が私の琴線に触れたということもむろんあるだろうが、だとしても、琴線に触れたのは「壊れました」というセリフのうち「壊れる」という動詞の意味内容ではなく、「ました」が指示するものごとのほうであったのは確かだ。すなわち、「壊れました」ということがデスマス口調の過去形で語られ、かつその後に「…と語った」という語句が続かなかったという事実によって、私はどうやら震撼させられたとおぼしいのであるが、これがどういうことかというと、あえて記すならば、上に引用したナレーションは初見時の私には以下のように聞こえたということである。
村のある人が、われわれに語った。「開発といっても、実際に工場が来るのはまだまだ先のことでしょう。公害防止の技術も進んでいくはずです。しかし、工場や公害が来なくとも、もう、村は壊れました。
上の最初の引用と、この2度目の引用の違いは、「語った。」と「開発」の間に「カギかっこ(「)」 が入っているという一点のみである。「われわれに語った」と言われ一旦そこで文が切れるからには、「開発といっても…」以下のセリフはひとまず間接話法として聞こえるのであり、「…のことでしょう」「…はずです」とデスマス調で語られたとしてもあくまでもそれはナレーターが「ある人」のセリフを引用して語っているものとして聞き、「引用」が終われば「…と語った」等の締めくくりが何かしらあるものという前提で聞く。この箇所のナレーションにおいてはあたかも英文か何かのように最初に「ある人が、われわれに語った」と言われていて、であるからには締めくくりとしての「…と語った」がなくとも語法として決しておかしくはないのだが、それでも、潜在的には「…と語った」という、書き言葉ならば定めし「カギかっこ閉じ」に当たる何らかの指標、ブイのようなものによって「引用」が締めくくられるだろうという前提が、聞く耳のどこか奥のほうにある、それが、案に相違して全く聞こえなかった、すなわち言わば「カギかっこ閉じ」がなかったのだ。間接話法だと思って安心して聞いていたのが、私の耳においていつのまにか直接話法にすり替わっていたのである。これは驚くべきことであった、なぜならば、直接話法にすり替わったということは、その時点から語り手がナレーターではなくなったということであり、ナレーターでなくば誰なのかといえば、最初に「…と語った」と言われた「ある人」でしかありえないが、ではその「ある人」とは誰か、それは文字通り「ある人」、a person、あるいはsomeone以外の何者でもなく、「音源としての姿を一度も見せない」のみならず、ナレータですらないそれがそもそも誰なのか全く不明なままに声だけが唐突に出現したところの純正アクスメートルに他ならない。「村のある人」、それはこの『巨大開発』という作品に登場する六ケ所村の人たちのうちの誰でもありうるが、同時に、全く登場しない人たちのうちの誰でもありうる。それは「佐藤さん」とか「戸田さん」とか「光志さん」とか固有名を与えられた数少ない人たちのうちの一人かもしれないが、そうであればなおのことそれは、「佐藤さん」や「戸田さん」でなく「村のある人」と呼ばれ直した時点でいっそう無名化した「誰か」であるとしか言いようがない。ナレーションはそれまでずっと、「六ヶ所村を訪れた」「われわれ」の視点で語っていたのに、いきなり、その「われわれ」が解体してしまい、誰だかわからない「村のある人」である「わたし」へと変貌してしまう。「わたし」という人称は音声としては聞こえないが、言うなれば「我語る、ゆえに我あり」という形式における一人称が出現して、画面とその視聴を支配する。私は何を見せられているのか――「わたし」が見ているものを見ているのか、それとも、「わたし」を見ているのか、画面の「外にも内にも」「わたし」のいる位置を特定できないまま、その「わたし」の声が「掟であるかのように現れ」、その声で語られる「もう、村は壊れました」という言明が抗いえない判決のように轟く。「同時に内部でも外部でもある〔画面の〕表面を漂い」、そのため「偏在性」と「すべてを見通す」力を備え、「掟であるかのように現れる」アクスメートルは、直接話法へのすり替わりと共に現れ、ナレーションとも「村人のセリフ」ともつかぬ位置から波濤とともに画面の表面に飛沫き漂い、「六ケ所村」と開発をめぐる「すべてを見通す」偏在する何者かの視点を以て私を身動きできぬまでに刺し貫く。それは全くの不意打ちである――間接話法から直接話法へ、いつ、どの時点で移り変わったのかと問うことにはおそらく意味がない。この震撼は、「…ました」と言われてからその余韻が失せるまでの0.1秒かそこらの間に起こるとすれば起こるのであって、気づいたときにはすでに語り手が移り変わっていた、ということがその0.1秒の間に事後的にわかるだけである。「私は誰の声を聞いているのか?」とリアルタイムで問う暇などまるで与えられず、仮に何かを問う余裕があったとしても、それは「いま誰の声を聞いてしまったのか」という形でしか問い得ないような、ほとんど悔いに似た問いになる他はない。「もう、村は壊れました」「壊れました」「……ました」、それは絶対的な過去形であり、覆すことのできない圧倒的な断定であり裁定であり、それを前にしてそこから先へは一歩も進むことのできない逆巻く波濤の壁であり、私はその判決の轟きに麻痺したようにそこに立ち止まり、白く飛沫くうねりに目をふさがれながら立ち尽くしているしかない。
「村は壊れました」、その言明がアルファでありオメガであるような、否定すべくもない裁定は、しかしあくまでも、それまでの30数分の間に映し出され私が見聞きしてきたところの「村」に対して下るのであり、1973年に実在した青森県六ケ所村に対して下るのではない。実在の六ケ所村は数々の危機を苦しみ乗り越えながら今も存続していて、つい数年前にも原発廃棄物処理施設をめぐる新たなドキュメンタリー映画が撮られたはずであり、73年時点で壊れてしまった部分が実際に諸所あったとしても、全面的に崩壊し果てたわけではなく、自分たちの村が壊れてしまったと嘆く人もいれば、いいやまだまだこれからだと奮起した人々も多くあっただろう。繰り返すならば、この『巨大開発』が映し出す「六ケ所村」の真実があるとすればそれはあくまでもこの映像作品において立ち現れている六ケ所村のそれであって、現実の六ケ所村のそれとは全くイコールではないし、30数分私が見聞きしてきたような六ケ所村は、この作品においてしかないところの六ケ所村である。「村は壊れました」と裁定されるその「村」は、そのような、この作品に映し出されている限りにおいてあったところの村で、それゆえにその裁定は覆しえない。私はまさにその「村」が徐々に「壊れて」いくのを、ショット構成とナレーションの導きに従って刻々と目のあたりにしてきたのだし、そのあげくに「壊れました」と断定され、ああ、壊れたのだなと、物語はこの先どこへも行けないのだなと無理にも納得する以外何ができるというのか? この海には、もう出られません。漁業が次第に縮小し、今では村人自身が日々の糧の足しにするためにのみ「楽しい共同作業」として行っているという地引網漁、その豊かな収穫を前に無邪気に手をうって喜ぶ村の女たちの姿がいっとき私の心を和ませた、そのような漁も、すでに過去のものとなった。先祖の墓に集まって戸外の食事を共にする盆祭りに見られた子供らの笑顔も、毎夏の村民運動会の高揚も、それらはみな、とうに「壊れました」。――随所でナレーションが「代弁」するときに言われる「〇〇さんは……と語った」とか、「不動産業者が乗り込んだ」とか、それらの過去形は、あくまでもナレーターが、実在した取材班の代表として彼らと彼らが取材した村との関係性を語るにあたって投入した過去形で、ナレーターのいう「われわれ」が自分たちの過去において行った取材に関して現在報告をしているという意味ではあくまでも現在進行形の語りであり、その現在進行性は、彼らのレポートを視聴している私のその視聴における現在進行性と合致している。それに対してこの海のシーンにおいてのみ唐突に屹立するこの過去が圧倒的な過去であって、年代を特定することのおよそ不可能な絶対的な過去であるのは、それがひとえに「ました」という過去形の持つ、過去という形式、においてのみ純然と立ち現れる過去、語り手が何らかの地平においてものを語るその語りの現在性を欠いた、純然と形式的な過去だからだ。アクスメートルの「偏在性」はおそらく空間的のみならず時間的にもその権能を発揮する。私の目の前に打ち寄せている波濤は、いま現に私の目の前に打ち寄せている波濤以外の何物でもなく、それは、いま現にそこに打ち寄せていて、「…は壊れました」という判決もまた、今その瞬間において下される、しかしその判決において、その現在を、形式としての過去が圧倒し去る。
ロラン・バルトの有名な写真のノエマの話――写真は常に「それは・かつて・あった」というところへと鑑賞者の意識を向ける、という話に、私はかつて心底納得したことがなかった。バルトのこの話にというよりも(バルトのそもそものテクストをきちんと理解してはいないのかもしれないから)、このことに基づいて写真や映像一般を論じることで何かが語れるだろうとする態度に私はずっと抗おうとしてきたし今もしている、というのも、写真を介した鑑賞者と被写体との関係性においては、「それは・かつて・あった」というところへ意識を向けられるという局面は確かにあるだろうし、それは重要な局面でもあろうけれども、写真を観賞する、あるいは映像を視聴する局面、すなわち映像とそれを見る者とのダイレクトな関係性においてそもそも被写体はすでに何ら介在してこないのであり、写真とその被写体とを鑑賞者の意識において繋ぎあわせるのは、外部情報それも専ら言語情報でしかないからである。『巨大開発』に映し出されているような村に似た村が、実際どこかに「かつて・あった」かどうかは、字幕やナレーションや解説文によって語られない限り誰にもわかりはしないし、語られたとしても、それは『巨大開発』という作品の素材映像がその実在の六ケ所村での取材において取得されたという以上のことを保証するわけではなく、そこに、被写体であったところの六ケ所村がありのままに映っているわけでも何でもない、そこに映っているのは、私がそれを見るとき私の目に映っている限りにおいて存在する村、今そこにある村である。しかしその現在性が、形式的な過去形によって圧倒し去られるとき、「それは・かつて・あった」/「それは・すでに・ない」というノエマ、意識の方向づけが、映像という媒体それ自体に内包される厳然たる法として改めて呈示されるかのようであり、このとき「それ」は、被写体を指すのではなく、私の目に映っている限りにおいて存在していたところのものそれ自体を指す。私が見ているものは、私が見ている限りにおいてそこにある、という現在形の言明において映像を見ることを、映像は私に対して要請する、なぜならばそうでなければ私は映像をではなく被写体を見ることにしかならないからだ。しかしその一方で、私が見ているものは「もう壊れました」――かつてあったが、今はなくなりましたという過去形の言明を付与されることを拒絶することは、映像にはできない。そもそもそれ自体無文脈であるところの映像は、まさにそれゆえにあらゆる言語的文脈によっても容易に回収されてしまうが、映像というものがそもそも撮影されたものであるというところに出自を持っているがゆえに、「かつて・あった」という包括的な文脈がアクスメートルの圧倒的な権能を以て襲いかかってくるときにそこから逃れ去ることはおそらく、いかなる映像にとっても不可能なのではあるまいか。視聴者の私がいかに抗おうとも、映像自体が、抗いえない、なぜなら映像は所詮映像であって、spookyに出現しては失せゆき、そこに映らなくなれば存在しなくなるもの、私が今げんにそれを見ているのでない限り、一瞬前に見たものですら、すでにそこにないものだからだ。私が見てきた村、それが「壊れました」ということは、否定すべくもない端的な事実として告げ知らされるのである。
4 残余
その後、牛が売られてゆき、新納屋地区では新年の祭りがいつものように賑やかに楽しまれるが、それらの光景は、すでに壊れたものの残滓、あるいは取り片付けの作業、あるいは名残の夢のようなものとして見える。新納屋の祭り囃子はやがてエコーがかかって、雪原に吹きすさぶ風の荒涼たる音響の中に溶けてゆき、「年間の平均気温9.3度……これまで誰にも知られることのなかった、目立たない小さな村の歴史である」等々というなおも淡々としたナレーションを以て45分の動画はしめくくられる。最後にもう一度『巨大開発』の題字が出るときその背景はひょうひょうと寒風が鳴る人っこひとりいない冬の雪原である。

春の菜の花畑を背景とした題字から始まって、ちょうど季節がひとめぐりしたことになる。見たものがすべて「壊れ」、すでになくなった私の脳裏には、雪原と、海と、思いのほかにユリ、馬、白鳥そして黄金色の芦原の光景だけが、壊れずに残っていた。それらはもともと「村」と「開発」をめぐる一連のものごとから外れたところに位置して見えていた光景であり、外れていたがゆえに、「村が壊れ」たその崩壊を辛くも免れたものたちだということなのだろうか。
上に引いた片岡論文には、シオンによれば「声を発しない無言の人物は、物語の「探求の鍵となる究極の一声を匿っているように推定され」る」とあり、いっとき私は、「無言の人物」すなわちミュエたる「光志さん」が「匿っているように推定される」「探求の鍵となる究極の一声」こそ、この「もう、村は壊れました」の一声なのではないかと考えてみていた。「村のある人」とは「光志さん」のことであり、ミュエとしての「光志さん」が秘匿しているこの「究極の一声」を、時間差をもってアクスメートルが放つことによって、ミュエ/アクスメートルの権能が「相補的」に瞬間最大の力を発揮しているのではないかと。しかしそれではあまりにも理に落ちすぎ、綺麗な図式ができすぎ、話がうますぎるとも思うのであった。そもそもカメラが「光志さん」を回り込み、彼の沈黙の秘匿性を最もあららかに呈示するのは、海のシーンの後、すなわちものごとが「壊れた」後なのである。彼の沈黙の中に「匿われた」「一声」があるとすればそれは、村が「壊れた」後、「壊れました」という判決の後になお残る一声でなければならないだろうと思われた。
私は幸いにしてこの『巨大開発』をリアルタイムの放映で見たわけではなく録画映像で見ていたから、壊れましたと言われて一旦茫然とはしたものの、幸いなことに何度でも再生して見直すことができた(これが一回きりの放映で、二度目を見る可能性がいつかあるともないとも知れない状況で見たとしたら、果たしてすみやかに立ち直れたかどうか全く自信がない)。村議会騒乱の場面は何度見ても見飽きない迫力に満ちており、要所々々以外きわめて聞き取りにくい方言言葉も、繰り返し聞くうちに少しずつ聞き取れるようになっていく。開発を受け入れるか受け入れないかの議決の正念場で、追い込まれた反対派の村長は、自陣に近く反対派住民の多い地区に議場を移してそこで決戦に挑もうとするが、賛成派の議長はじめほとんどの議員はこれに抗い、数を頼んでいつもの議場で議会を強行開催、村長不在のまま、開発受け入れ案を一括上程・承認へ持ち込んだ。あれよあれよという間に議決が成ってしまったのを見て、傍聴していた反対派の市民たちはただちに議長席に詰めかけ、くちぐちに詰問する――「もっと! 正々堂々とやったらどうです、議長さん!」「……だめ!…議長…!だめ!」「…おらとこの代表でねえですかアンタがた!…んて!無責任なことやンのヨッ!」「正々堂々と!」「…てイイことと悪いこととあんだよ命がかかってんだヨこれは!」「こったらものに!この六ケ所村まかすてたまるものか。やい」「…無視して…議会…今の世の中にありますかこの民主…!」「そうだそうだ!」強い訛りといやましの興奮によってほとんどの叫びは聞き取れず、机をばんばん叩くその音、必死の表情や体の動き、喧騒そのものから、その場のどうしようもないコンフリクトがマッスの形で看取されるのだが、最初あっけにとられてたじたじと「静かに」「騒がねいで」となだめる一方だった議長が、ある時点で腹をくくったかのように反撃に転じる。「私はね村長こそ! 開発の(……)を進めてきたと私は断固に(?)こう言います」この(……)と(?)の部分はどうしても聞き取れないが、続いて「なぜ地権者を説得しねのかッ!」との一喝に、喧騒はシンと静まってしまう。「…反対なのであるならば! なぜ(……)の、弥栄の地権者を説得しねのかッ!」そのあと賛成派の傍聴者とおぼしい人の声が議場の後ろのほうから「そうだ」「村長が悪い!」などと聞こえてき、カットが入った直後には議長はもう余裕の勝利の笑みを湛えて議場を立ち去るところで、「騒いで」いた人々はもはやそれを引き留める力もなく、ただ追いすがるように「反対するための反対じゃないんですよ!」「おらたち……今の開発がおそろしいと思うから反対するのであって、絶対、騒ぐための、反対するための反対じゃないんですよ」と、すでに議長も議員たちもいなくなった議場で、取材班に向かって泣くように言うしかない、その目を覆うばかりの敗北感が痛ましくも惨憺たるものである。「実際の」議会ではもっと長くこの騒乱は続いたであろうし、論戦ももっと錯綜した展開をしたであろうことは想像に難くないが、私が見る「この」村会騒乱の場では、議長の一喝が明瞭に場のムードを変えた。「反対なのであるならば、なぜ(……)の、弥栄の地権者を説得しねのか」というセリフがなぜ人々を黙らせたのかを考えると、(実際の六ケ所村でどうだったかはともあれ)少なくとも「この」村では、名前の聞き取れないいくつかの地区および「弥栄」地区の地権者が多く土地を手放し補償金をもらって立ち退く決断をしたことが、村全体の開発受け入れの方向性を決定的なものにしたのであろう、という推測が成り立つ。「戸田さん」のいる「上弥栄地区」は酪農地帯で、「一戸あたりの経営面積が広く、補償金の額も大きい」と、最初のほうでナレーションが語っていた。これらの地区の人々の多くが「戸田さん」同様の決意をして早々と立ち退く方向へ動いたのであって、村長含め反対派の人々が本当に開発を止めたいならば、まずこれらの大土地権者をこそ引き留めるべく運動すべきだった、と議長は言うのである。広い土地を所有する彼らが立ち退きを決意した以上、村全体として開発を拒否することなどできっこないのだ、とそういう論法なのであろう。その論法の是非はともかくそれに対して反対派の人々は抗弁できなかった。上弥栄地区の「地権者」である「戸田さん」は、やっと丹精した牧場を苦渋の思いで手放さざるをえなくなり、「県外の業者」に牛を買い叩かれても泣く泣く我慢するしかなく、貸家業を始めるといっても不安だらけで、頼れるのは無口な痩せっぽちの息子だけというような、寄る辺ない感じの人として登場するのだけれども、この議会騒乱の場においてはその「戸田さん」は、村の平穏のために土地を死守して闘うよりも巨額の補償金に代えて土地を手放すことを率先して選んだ「地権者」の一人なのであり、開発に「賛成」したわけではないにせよ結果的に開発受け入れの流れを作った責任者の一人として反対派から恨まれる立場の人なのである。黄金色の芦原を背景に「ほんとに悔しい」という内心を吐露する「戸田さん」だが、「戸田さん一家」としてのその決断には当然、出稼ぎ先の東京で事故にあって入院中だという夫の意向、そして「跡継ぎ」である「光志さん」の意向も色濃く反映していたことだろう。彼らの意向について全く言及されないのも、見ようによっては実に「あざとい」手法だと言え、実在の「戸田さん」一家の実情とはかかわりなく「この」「戸田さん一家」は、ひょろりとした19歳の頼りなげな息子と中年の母親だけが寄り添って暮らす母子家庭として呈示され、寄る辺ない無力なその家庭が開発という巨大な力の前に押しひしがれ屈していくという側面のみにひとまずスポットが当てられる。しかし「戸田さん一家」が決してそのような単線的な属性付けに甘んじるものではないことが、はしなくもこの議長の一言、「なぜ……弥栄の地権者を説得しねのか!」においてあらわれ出る。そして同時に、開発が来なければやがては牧場を一子相続することになったであろう「光志さん」の沈黙もまた、単にその内に「村が壊れてしまった」という悲痛な感慨をのみ「匿って」いるものでは決してないであろうことが、むしろ希望的に看取される。そうでなくとも、「内心が読み取れない」ということは、言い換えればその「内心」なるものはいかなる方向性へも開かれているということであり、実在の光志さんが仮に村の崩壊を心から悼んでいたにせよ、逆に実は開発に大いに賛同していたにせよ、それとは関わりなく沈黙している「この」「光志さん」は、いかなる「究極の一声」をも発しうる無限の可能性をこそその沈黙のうちに秘匿している。「村は壊れました」というナレーションに続き、「しかし…」あるいは「そして…」等さまざまな接続詞が発せられる可能性、そしてそれらの接続詞に続いていかなる発語がなされる可能性も、この沈黙は平等に内包しているのであり、「村は壊れました、ぼくはとても悲しい」とか「バカヤロー」である可能性もあるけれども、「村は壊れました、確かにね、でも残ってるものもたくさんある」とか、「村は壊れました、それは確かに寂しいことだけど、正直言うと、この牧場を継がなきゃならないというのがぼくにとってはすごく重荷だったんで、そういう意味ではホッとするような気持ちもありますね」とか、さらには「村は壊れた、だから何なの?」とか「ぼくには別に関係ない」とかである可能性さえそこでは否定されない。彼はいつか村に戻って新たな村おこしに邁進してもいいし、都会に出たっきり帰ってこなくてもいいし、何なら豪華なシャンデリアをしょった実業家として何十年後かにさらなる用地買収に訪れても構わない。そういう自由が、彼には残されている。それが製作者の意図によるものかどうかはわからない。パンドラの箱に希望が残されたように、「光志さん」というミュエの沈黙に、いまだ壊れていない希望を秘匿し託すというようなことを製作者が考えて作ったのか、あるいは、ひょっとして取材中に光志さんが本当に「ボクには関係ないね」などと標準語で喋ったのが編集方針に照らして「使えない」とみなされ棄てられた結果として、上のように見えるような仕上がりにたまたまなっただけなのか、それはわからないことだし、わからなくて構わない。私は、「これまで誰にも知られることのなかった、ある小さな村の歴史」を見、その崩壊を見たが、崩壊の後になお、ユリと馬と白鳥と、黄金色の芦原が、政争の文脈に絡めとられずに勝手放題なありかたをし続けることができるかもしれない希望の表象として、ひとりの若者の沈黙のなかに、不安定にしかし確かに残っているのをもまた、今は見ることができるようになった。
2021.07.05
